わかりやすい説明と
丁寧なサービス
Easy-to-understand explanations and attentive service

About us
事務所概要
分かりやすい説明と
丁寧なサービスを
心掛けています
弊所は、滋賀県と大阪市北区に事務所を構えています。
ご依頼は、権利に関するあらゆる不動産登記、不動産や金融資産を中心とした相続手続、遺産分割協議の成立に向けた支援、遺言や家族信託等の遺産承継に関する業務、商業登記を中心とした会社法務、破産や民事再生などの債務整理業務、裁判所提出書類の作成、簡易裁判所における訴訟代理、帰化申請など、幅広く司法書士業務を行っています。
どの業務においても、仕事の質にこだわって最良の法務サービスの提供に努めています。
初めてご相談くださるお客様も歓迎しております。お気軽にお問合せください。
自分ならどのような人に依頼したいか
自分ならどのような仕事を期待するか
一人ひとりのお客様に「依頼してよかった」と感じていただけるよう、誠実に全力で業務に取り組みます。
事務所概要Case / Procedure
相談事例と手続
-
遺言・家族信託
妻と二人の子供がおります。
妻たちに残す財産として、土地と建物、小額の預貯金があります。特に大きな財産もありませんし、妻と二人の子供の仲も良好ですので、わざわざ遺言を残す必要はないのではと考えております。遺言は必要でしょうか。 -
遺言・家族信託
長女と長男の二人の子供がおります。
私を長年介護してくれている長女には、そのお礼として相続させる財産の割合を増やしたいと考えています。一方、長男には、以前自宅購入資金を援助しているので、その分相続させる割合を減らしたいと考えております。何か方法はありませんか。 -
遺言・家族信託
私には、妻、長男、長女の3人の家族がおります。
長男は前妻との間の子で、妻や長女と交流はありません。このたび、遺言を作成するにあたり、不動産は妻に、預貯金を子供2人に半分ずつ相続させようと考えています。
一般的に、相続手続は相続人が全員で行うようですが、長男と妻及び長女が連絡を取り合わずに相続を進めることができるように備えておくことはできますか。
-
債務整理
Aさんは、消費者金融5社から合計約230万円の借入がありました。
もともと専業主婦で、夫の収入(月収23万円)で家計のやりくりをしていたのですが、返済が困難になり、パートに出るようになりました。しかし、なかなか借金は減らず、パート収入では返済が追いつかなくなり相談に来られました。 -
債務整理
Bさんは、10年程前から消費者金融6社と取引があり、借入と返済を繰り返してきました。
ここ1年は、毎月の返済が15万円を超えるまでに膨れ上がり、支払いが困難な状況でした。
契約当初は20%を超える金利で契約しており、取引期間も長いことから、「すでに過払いになっているのではないでしょうか」、「返ってこなくてもいいので少しでも返済が楽になりませんか」と相談に見えられました。 -
債務整理
Cさんは、約14年前に消費者金融から合計約500万円の借入れを行いました。
14年間返済を続け、2年前に退職金でようやく完済することができました。知人が債務整理をして過払金が返ってきたことを聞き、ご自身にも当てはまるのではないかと考え相談に見えられました。 -
債務整理
Dさんは、信販会社や消費者金融10社からの借入れと住宅ローンがあり、利息の返済もままならず、たびたび債権者から電話がかかってくる状態でした。数年前に離婚し、子供は成人しているので、今は一人暮らしとのことです。
定年退職後はアルバイトで生計を立てておられましたが、収入が大幅に減ったことで、返済が追いつかなくなりました。銀行に対して金利を下げてもらえないかと相談されましたが、断られたようです。このままでは借金の返済のためにアルバイトをする毎日だと悲観的になり、精神的にも相当疲弊しておられました。
そして、自宅を処分して自己破産できないものかと相談に来られました。
-
その他の業務
夫と死別し子供はおらず、マンションでひとり暮らしをしています。
近くに親族もおらず、老後の生活や財産管理のことを考えると不安です。
何かあった場合に備えて準備しておくことはできますか。 -
その他の業務
突然、弟が脳梗塞で倒れました。弟は植物状態になり回復の見込みがないと診断されました。
弟の妻は数年前に亡くなっています。また、弟には多額の借金があり、借金の返済や施設への入所のことなど、この先どうしたらいいのか私自身も高齢のため困っています。 -
その他の業務
知的障害のある弟がおります。
両親の死後は私が世話をしてきたのですが、長年にわたる介護の負担から体調を崩しました。
このままでは、私の生活にも支障が出てきそうです。解決策はありますか。 -
その他の業務
80代の母は、ひとり暮らしをしております。
最近、物忘れがひどくなり判断力が衰えてきたと感じていました。
先日実家に帰省した際に、母が訪問販売で高価な布団を購入していたことを知りました。
今後も同様の被害に遭わないか心配です。

お問合せ・相談申込
お気軽にご相談ください。
 メールでご連絡
メールでご連絡
内容を確認のうえ担当者からご連絡いたします

ご相談可能
相談専用ダイヤルまたはメールにてお問合せのうえご予約ください。
相談専用ダイヤルまたはメールにて
お問合せのうえご予約ください。
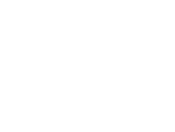
オンライン相談
パソコン・スマートフォン・タブレットなどでZoomを利用して相談が可能です。
ご希望の方は電話またはメールにてお知らせください。


 お問合せ
お問合せ









